風景画や水彩画を学ぶのにオススメの本が知りたいな。できれば、種類別・目的別にオススメの本が知りたいな
こういった悩みにお応えします。
✔︎ 本記事の内容
1.透明水彩画の基礎知識や描き方について勉強したい初心者の方におすすめの本2冊
2.水彩絵具を使って風景画を描いているけど、なかなか上達せずに悩んでいる方にオススメの本1冊
3.風景画のスケッチやデッサン、水彩画の下描きが苦手で上手く描けずに悩んでいる方にオススメの本2冊
4.遠近感のある風景画や水彩画を描くために、遠近法を勉強したい初心者の方にわかりやすくてオススメの本1冊
5.透明水彩画の色の作り方・混色について勉強したい方におすすめの本1冊
この記事を書いている僕は、風景画や水彩画の勉強は3年ほどです。
普段本を使って勉強しています。
こういった僕がわかりやすく紹介していきます。
目次
透明水彩画の基礎知識や描き方について勉強したい初心者の方におすすめの本2冊
1『今日から描ける はじめての水彩画』
この 『今日から描けるはじめての水彩画』を読むと、
・水彩画を描くための基礎的な知識や技法
が身につきます。
なので、これから水彩画を始めてみたい! という方に特にオススメです。
なぜ、水彩画を描くための基礎的な知識や技法が身につくのか、というと、
この 『今日から描けるはじめての水彩画』では、水彩画の基礎力を身につけるため、
道具の使い方から、実際の描き方のプロセス、そして、コツまでを網羅的に解説しているからです。
そして、その解説では、
・どんなタッチで描いているのか、
・どんな塗り方をしているのか、
がわかるように、
写真を拡大したり、描く際のワンポイントアドバイスを紹介するなど、
しっかりと力がつくように、工夫されています。
そのため、実践すれば、水彩画を描く上での基礎的な知識や技法を身につけることができます。
よって、これから水彩画を始めてみたい! というあなたも、
水彩画を描くための基礎的な知識や技法を身につけることができます。
以下の記事で詳しく紹介しています。
2 『野村重存 「水彩スケッチ」の教科書』
この『野村重存 「水彩スケッチ」の教科書』を読むと、
・テーマ(静物、風景、動物、人など)ごとの描き方と、
それを描く際にポイントとなる、筆の使い方や塗り方といった着色技法
が身につきます。
なので、
これから水彩画を始めてみたいけど、
描き方や筆の使い方、塗り方といった基礎部分をしっかり身につけたいという方に、特にオススメです。
なぜ、テーマ(静物、風景、動物、人など)ごとの描き方と、
それを描く際にポイントとなる、筆の使い方や塗り方といった着色技法が身につくのかというと、
この『野村重存 「水彩スケッチ」の教科書』では、
テーマごとの描き方と、
それを描く際にポイントとなる筆の使い方や塗り方といった着色技法を、
拡大写真と連続写真で学べるからです。
そして、その拡大写真では、
鉛筆や筆を使って、どういうタッチで描いているのか、塗っているのか、が詳細にわかります。
また、連続写真では、制作の全体の流れが詳細にわかります。


こんな感じで描いていけばいいのか!
こんな感じで塗ってるのか!
みたいなのがよくわかります!
なので、真似して実践するだけで、描き方や着色技法が身につきます。
つまり、どんなタッチで描いているのか、どんな感じで塗っているのか、
が詳細にわかる本書『野村重存 「水彩スケッチ」の教科書』を実践すれば、
あなたもテーマごとの描き方や、
その際ポイントとなる、筆の使い方や塗り方といった着色技法を、身につけることができるのです。
以下の記事で詳しく紹介しています。
水彩絵具を使って風景画を描いているけど、なかなか上達せずに悩んでいる方にオススメの本1冊
3『たった10日でうまくなる「水彩画」の基本 風景を描くコツと裏ワザ』
この『たった10日でうまくなる「水彩画」の基本 風景を描くコツと裏ワザ』 を使うと、
① 「絵になる構図」の見つけ方
② できあがりに差がつく「下描き」テクニック
③ 「遠近感」のある絵を描く大切なルール
④ 「水彩絵具」の使いこなし方
⑤ 絶対に失敗しない「着色」のプロセス
⑥ 明暗を分ける「立体感」の出し方
⑦ プロが実践している「水や空」の表現法
⑧ 風景画に欠かせない「森や樹木」の描き方
⑨ さまざまな「風景素材」を描く、それぞれのコツ
⑩ 最後の「仕上げ」は、細部にこだわる
上記10項目の、水彩絵具で風景をより上手く描くためのコツ・裏ワザ
が身につきます。
なので、
水彩絵具を使って風景画を描いているけど、なかなか上手く描けないな…。なんか全然上達しないし。もっと上手く風景を描けるようになりたいな
と悩んでいる方に、特にオススメです。
では、なぜ、
① 「絵になる構図」の見つけ方
② できあがりに差がつく「下描き」テクニック
③ 「遠近感」のある絵を描く大切なルール
④ 「水彩絵具」の使いこなし方
⑤ 絶対に失敗しない「着色」のプロセス
⑥ 明暗を分ける「立体感」の出し方
⑦ プロが実践している「水や空」の表現法
⑧ 風景画に欠かせない「森や樹木」の描き方
⑨ さまざまな「風景素材」を描く、それぞれのコツ
⑩ 最後の「仕上げ」は、細部にこだわる
上記10項目の、水彩絵具で風景をより上手く描くためのコツ・裏ワザ
が身につくのでしょうか?
それは、
① 「絵になる構図」の見つけ方
② できあがりに差がつく「下描き」テクニック
③ 「遠近感」のある絵を描く大切なルール
④ 「水彩絵具」の使いこなし方
⑤ 絶対に失敗しない「着色」のプロセス
⑥ 明暗を分ける「立体感」の出し方
⑦ プロが実践している「水や空」の表現法
⑧ 風景画に欠かせない「森や樹木」の描き方
⑨ さまざまな「風景素材」を描く、それぞれのコツ
⑩ 最後の「仕上げ」は、細部にこだわる
上記10項目の、水彩絵具で風景をより上手く描くためのコツ・裏ワザ
を、カラー写真や水彩イラストを使い、簡潔にわかりやすく解説しているからです。
例えば、⑧ 風景画に欠かせない「森や樹木」の描き方のモコモコとした立体感のある木の描き方部分では、
モコモコと立体感を出すためには、まずこういう点を意識すべきというコツ・裏ワザを紹介し、
そして、モデルになった木のカラー写真と共に、その木を水彩絵具で描くためのプロセスを、
実際の水彩イラストを使い、簡潔にわかりやすく解説しています。
そして、本書『たった10日でうまくなる「水彩画」の基本 風景を描くコツと裏ワザ』は、
① 「絵になる構図」の見つけ方
② できあがりに差がつく「下描き」テクニック
③ 「遠近感」のある絵を描く大切なルール
④ 「水彩絵具」の使いこなし方
⑤ 絶対に失敗しない「着色」のプロセス
⑥ 明暗を分ける「立体感」の出し方
⑦ プロが実践している「水や空」の表現法
⑧ 風景画に欠かせない「森や樹木」の描き方
⑨ さまざまな「風景素材」を描く、それぞれのコツ
⑩ 最後の「仕上げ」は、細部にこだわる
上記10項目の、水彩絵具で風景をより上手く描くためのコツ・裏ワザ
を、10日間10項目という形に整理し、1日目、2日目…という感じで繰り返し反復練習できるように工夫しています。
具体的には以下のとおりです。
◻︎1日目「絵になる構図」の見つけ方
◻︎2日目 できあがりに差がつく「下描き」テクニック
◻︎3日目 「遠近感」のある絵を描く大切なルール
◻︎4日目 「水彩絵具」はこうして使いこなす
◻︎5日目 絶対に失敗しない「着色」のプロセス
◻︎6日目 明暗を分ける「立体感」の出し方
◻︎7日目 プロが実践している「水や空」の表現法
◻︎8日目 風景画に欠かせない「森や樹木」の描き方
◻︎9日目 さまざまな「風景素材」を描く、それぞれのコツ
◻︎10日目 最後の「仕上げ」は、細部にこだわる
このように、10日間10項目という形で整理されているので、
自分が特に苦手な部分を重点的に練習することができ、効率的に習得が可能です。
つまり、
① 「絵になる構図」の見つけ方
② できあがりに差がつく「下描き」テクニック
③ 「遠近感」のある絵を描く大切なルール
④ 「水彩絵具」の使いこなし方
⑤ 絶対に失敗しない「着色」のプロセス
⑥ 明暗を分ける「立体感」の出し方
⑦ プロが実践している「水や空」の表現法
⑧ 風景画に欠かせない「森や樹木」の描き方
⑨ さまざまな「風景素材」を描く、それぞれのコツ
⑩ 最後の「仕上げ」は、細部にこだわる
上記10項目の、水彩絵具で風景をより上手く描くためのコツ・裏ワザ
を、カラー写真や実際の水彩イラストを使い、簡潔にわかりやすく解説し、
さらに、それを効率的に習得できるように、10日間10項目という形に整理し、繰り返し反復練習できるように工夫した
本書『たった10日でうまくなる「水彩画」の基本 風景を描くコツと裏ワザ』を実践すれば、
① 「絵になる構図」の見つけ方
② できあがりに差がつく「下描き」テクニック
③ 「遠近感」のある絵を描く大切なルール
④ 「水彩絵具」の使いこなし方
⑤ 絶対に失敗しない「着色」のプロセス
⑥ 明暗を分ける「立体感」の出し方
⑦ プロが実践している「水や空」の表現法
⑧ 風景画に欠かせない「森や樹木」の描き方
⑨ さまざまな「風景素材」を描く、それぞれのコツ
⑩ 最後の「仕上げ」は、細部にこだわる
上記10項目の、水彩絵具で風景をより上手く描くためのコツ・裏ワザ
は、あなたも身につけることができるのです。
風景画のスケッチやデッサン、水彩画の下描きが苦手で上手く描けずに悩んでいる方にオススメの本2冊
4『こう描けば、そう見える! 水彩画「下書き」の裏ワザ』
この『こう描けば、そう見える! 水彩画「下書き」の裏ワザ』を使うと、
「こう描けば、そう見える」という水彩画の下描きの描き方
が簡単に身につきます。
なので、
水彩画の下描きを上手く描きたいけど、なかなか上手く描けないな…
と悩んでいる方に、特にオススメです。
では、なぜ、
「こう描けば、そう見える」という水彩画の下描きの描き方
が簡単に身につくのでしょうか?
それは、本書『こう描けば、そう見える! 水彩画「下書き」の裏ワザ』で紹介している
「こう描けば、そう見える」という水彩画の下描きの描き方
は、全て
◇、☆、→、井、ハ、冊
といった図形や記号、文字だけで描ける描き方だからです。
具体的な内容は、以下のとおりです。
◻︎Part ① 建物や道の下書き
・四角い建物は「ホームベース」で形をとらえる
・屋根や軒先の傾斜角度は「時計の針」で確認する
・建物は「井」の字でアタリをつけると形がとりやすい
・「かぎカッコ」を組み合わせると、窓になる
・アーチ状の形は、「円」を利用して描く
・道は「ハ」の字で描くと奥行きが出る
・「建物のある風景」 「坂道のある風景」
・「アーチのある建物」 作例プロセス
・「なぞり描き」練習帳
◻︎Part ② 山や森や木の下書き
・山並みは大小の「へ」の字を連ねていく
・草原は細かく乱雑な「川」の字で描く
・スギやカラマツの林は「M」字で描く
・「糸クズ」を描けば木の輪郭になる
・葉が生い茂った樹木は、「月見だんご」を想定して
・「ブロッコリー」をイメージしても樹木は描ける
・「スギの木」「山並み」 作例プロセス
・「なぞり描き」練習帳
◻︎Part ③ 花や花畑の下書き
・バラは「☆」と「カクカク渦巻き」を組み合わせる
・アジサイは「武田菱」をたくさん重ねて表現
・満開の桜は「雲」をイメージする
・菜の花畑は「ポップコーン畑」だった
・コスモスは「プロペラ」や「歯車」をいい加減に描く
・ラベンダーは「糸クズ」を「棒」にからめて
・「バラ」 「桜」 「アジサイ」 「ラベンダー畑」 作例プロセス
・「なぞり描き」練習帳
◻︎Part ④ 神社やお寺、木造建築の下書き
・神社仏閣の軒先は「品川描き」で乗りきる
・丸瓦の先端は「カッコ記号」が大活躍
・屋根瓦は平行線の間を「弓」の字で埋める
・板壁や窓は「囲」の字を並べたり、ゆがめたり、重ねたり
・石垣は「一筆描き」で迷路パズルを描くように
・「冊」を並べれば柵になる
・「城」 「伝統的町並みの風景」 作例プロセス
・「なぞり描き」練習帳
◻︎Part ⑤ 人の姿や顔の下書き
・人物の上半身は「釣り鐘」に見立てる
・「吊り金具」の位置を変えれば、さまざまなポーズを描き分けられる
・人の立ち姿は「シェイカーボトル」に見立てる
・目は「二重カッコ」と「U」の字を組み合わせて描く
・鼻は「ふ」や「い」「し」を使って
・口は「ニ」の字を逆さに描く
・「人のいる風景」 作例プロセス
・「なぞり描き」練習帳
そして、
◇、☆、→、井、ハ、冊
といった図形や記号、文字だけで描ける描き方なので、
どんなに絵が苦手な方でも簡単に身につけることができます。
つまり、
◇、☆、→、井、ハ、冊
といった全て図形や記号、文字だけで描ける描き方なので、
「こう描けば、そう見える」という水彩画の下描きの描き方
は、あなたも簡単に身につけることができるのです。
以下の記事で詳しく紹介しています。
5『野村重存「なぞり描き」スケッチ練習帳』
この『野村重存「なぞり描き」スケッチ練習帳』を使うと、
木や山や水、建物などの形を上手く描くために必要な鉛筆のタッチなどの、風景画の描き方のコツ
が自然と簡単に身につきます。
なので、
趣味で風景画や水彩画を描いているけど、デッサンやスケッチ、下描きが上手く描けないな…。 なので、風景画のスケッチや下描きを上手く描くためのコツが知りたいな
と思っている方に特にオススメです。
では、なぜ、どんな方でも、
木や山や水、建物などの形を上手く描くために必要な鉛筆のタッチなどの、風景画の描き方のコツ
が自然と簡単に身につくのでしょうか?
それは、本書『野村重存「なぞり描き」スケッチ練習帳』が、
木や山や水、建物などの形を上手く描くために必要な鉛筆のタッチなどの、風景画の描き方のコツ
を「なぞり描き」練習形式で身につけられるように設計されているからです。
☆ 著者で画家の野村重存先生の下絵を「なぞり描き」することで、
木や山や水、建物などの形を上手く描くために必要な鉛筆のタッチなどの、風景画の描き方のコツ
を自然と簡単に身につけられるように設計されています。
そして、それぞれの下絵の横には、「練習の目安」として、それらを上手く描くために意識すべきコツ、つまり、
木や山や水、建物などの形を上手く描くために必要な鉛筆のタッチなどの、風景画の描き方のコツ
が記載されています。
この
木や山や水、建物などの形を上手く描くために必要な鉛筆のタッチなどの、風景画の描き方のコツ
を意識しながら、実際に下絵を「なぞり描き」するだけです。
難しい練習方法ではなく、下絵をなぞって描くだけなので、
どんなに絵が苦手な方でも簡単に取り組むことができます。
なので、どんな方でも
木や山や水、建物などの形を上手く描くために必要な鉛筆のタッチなどの、風景画の描き方のコツ
を自然と簡単に身につけることができるのです。
つまり、
木や山や水、建物などの形を上手く描くために必要な鉛筆のタッチなどの、風景画の描き方のコツ
をなぞるだけで自然と簡単に身につけられるように設計された、
本書『野村重存「なぞり描き」スケッチ練習帳』を実践すれば、
あなたも、
木や山や水、建物などの形を上手く描くために必要な鉛筆のタッチなどの、風景画の描き方のコツ
を自然と簡単に身につけることができるのです。
以下の記事で詳しく紹介しています。
遠近感のある風景画や水彩画を描くために、遠近法を勉強したい初心者の方にわかりやすくてオススメの本1冊
6『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』
この『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を読み、実践すると、
イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ
が簡単に身につきます。
※ パース(透視図法)とは、遠近法の1つです。
パース(透視図法)ってそもそも何?という方は、
パースとは何か わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】
にてわかりやすく解説しているので参考にしてください。


遠近法には、様々な種類がありますが、その代表的なものがパース(透視図法)です。
風景画を描くための遠近法については、
風景画を描くための遠近法について わかりやすく簡単に解説します
でも詳しく解説しています。
この『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説している、パース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、
著者であり、漫画家・専門学校講師の椎名見早子先生が、
十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。
そして、その多くが、実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちからの質問をもとに作られたものです。
なので、
イラスト、マンガ、アニメーション、風景画などを描くために、
これからパース(遠近法)を勉強したいので、初心者にもわかりやすくてオススメの本が欲しいな
と思っている方に特にオススメです。
では、なぜ、どんな方でも、
イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ
が簡単に身につくのでしょうか?
それは、
イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ
をマンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説しているからです。
先程も紹介しましたが、
本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説しているパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、
著者の漫画家であり、専門学校講師の椎名見早子先生が、
十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。
そして、その多くが実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちの質問をもとに作られたものです。
なので、パースを初めて学ぶ方の目線に立って、そういった初心者の方がしっかりと理解できるように、
イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ
をマンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説しています。
例えば、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の解説部分では、
パースを学ぶ方が一番難しいと感じるアイレベルや消失点との関係性を、図を使って丁寧にわかりやすく解説しています。
また、パースの分割や増殖といったテクニック・ノウハウの解説部分でも、わかりやすく見やすい図解で丁寧に解説しています。
さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方がやりがちなミスや間違い、
そして、こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、ワンポイントアドバイスとして解説しています。
一般的にパース(透視図法)の解説書となると、難しい図や説明で解説されていることが多いです。
そのため、パースを初めて学ぶ方は、
「うわぁ…、パースってめちゃくちゃ難しくて全然わからない…」
という感じで挫折してしまいます。
しかし、本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』は、
パースを初めて学ぶ方でもしっかりと理解できるように、
マンガや、やさしい図、イラストを使って解説しています。
さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方が、やりがちな間違いや、
こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、
ワンポイントアドバイスとして解説しており、よりわかりやすいように工夫しています。
なので、「パースって難しくて全然わからない…」という感じにならずに学ぶことができます。
つまり、パースを初めて学ぶ方が理解できるように、
マンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説し、
さらにワンポイントアドバイスでよりわかりやすさを工夫した、
本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を実践すれば、
あなたも、
イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ
を簡単に身につけることができるのです。
以下の記事で詳しく紹介しています。
透明水彩画の色の作り方・混色について勉強したい方におすすめの本1冊
7『12色からはじめる 水彩画 混色の基本』
この『12色からはじめる 水彩画混色の基本』を読み、実践すると、
① 12色セットの絵具から2色ずつ組み合わせて混色すると、どんな色ができるのか
② そして、その色の作り方
③ その色の具体的な使いどころ、どこに使うと良いのか
という上記3つの知識が簡単に身につきます。
なので、
自分の作りたい、塗りたい色が上手く作れずに悩んでいるので、水彩画の色の作り方や、混色について勉強したい!
と思っている方に特にオススメです。
☆ この『12色からはじめる 水彩画混色の基本』は、はじめて透明水彩画を使って水彩画を描く方が、一般的に最初に多く使用する12色セットの絵具に焦点を当てて、上記3つの知識を解説しています。
では、なぜ、どんな方でも
① 12色セットの絵具から2色ずつ組み合わせて混色すると、どんな色ができるのか
② そして、その色の作り方
③ その色の具体的な使いどころ、どこに使うと良いのか
という上記3つの知識が簡単に身につくのでしょうか?
それは、
① 12色セットの絵具から2色ずつ組み合わせて混色すると、どんな色ができるのか
② そして、その色の作り方
③ その色の具体的な使いどころ、どこに使うと良いのか
という上記3つの知識を、
色見本と、著者で画家の野村重存先生が描かれたイメージ作例と完成作例を使って紹介しているからです。
色見本とは、ふせんくらいの大きさで2色の絵具を混色してできた色をグラデーションで塗って示したものです。


2色を混ぜると、「こんな色ができる!」というモデルのことです
なので、12色セットの絵具から2色ずつ組み合わせて混色すると、どんな色ができるかがパッと見ただけでわかります。
そして、この色見本と一緒に、
この色を実際に作るために必要な水の量と絵具の混色具合を「水の量」、「混色の比率」として記載しています。
具体的には、
・「水の量」を、小→多
・「混色の比率」を、色丸印の個数
という形で記載しています。


例えば、バーミリオンという色を5、クリムソンレーキという色を1の比率で混色し、水の量を、小→大と加えれば、この色のグラデーションができるという感じです
なので、この色を作るために必要な水の量と、どれくらいの比率で絵具を混ぜればよいのかが、視覚的に見ただけでわかります。


あ、こんな感じで絵具と水を配合すればいいんだね!というのがよくわかります!
さらに、こうしてできた色を具体的にどこに使ったらいいのかを、
著者で画家の野村重存先生が描かれたイメージ作例と、完成作例で紹介しています。
まず、イメージ作例の下に「Point!」として、
・〇〇 の △△ 部分の影色に使える
・〇〇 の ◻︎◻︎ 部分に使える
という形で紹介しています。
さらに、第3章では、混色で描いた完成作例で、それらの絵の、どの部分に12色セットの絵具の混色を使っているのかを紹介しています。
具体的には、
・この木のここの部分には、この2色を混色しています
・〇〇の影になっている部分には、この2色を混色しています
という形で紹介しています。


なので、あ、こういうところに使えばいいのか!、ここは、この色とこの色を混ぜて作ってるんだ!っていうのがよくわかります!
このように、
2色混色してできる色や、その色の作り方、その色の具体的な使いどころを、簡潔にわかりやすくパッと見ただけでわかるように記載しているので、
どんな方でも、
① 12色セットの絵具から2色ずつ組み合わせて混色すると、どんな色ができるのか
② そして、その色の作り方
③ その色の具体的な使いどころ、どこに使うと良いのか
という上記3つの知識を簡単に身につけることができるのです。
つまり、
① 12色セットの絵具から2色ずつ組み合わせて混色すると、どんな色ができるのか
② そして、その色の作り方
③ その色の具体的な使いどころ、どこに使うと良いのか
という上記3つの知識を、
色見本や、著者で画家の野村重存先生の作例を使い、
簡潔にわかりやすく紹介している本書『12色からはじめる 水彩画混色の基本』を読めば、
あなたも、
① 12色セットの絵具から2色ずつ組み合わせて混色すると、どんな色ができるのか
② そして、その色の作り方
③ その色の具体的な使いどころ、どこに使うと良いのか
という上記3つの知識を簡単に身につけることができるのです。
こちらの記事で詳しく紹介しています。
まとめ: 風景画・水彩画の勉強におすすめの本を種類別・目的別に7冊紹介
今回は、実際に僕が買って良かったなと思える水彩画や風景画に関する本を紹介しました。
今後もまた良いなと思える本があったら、追加していきます。
また、以下の各記事では、パース(透視図法)や人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。
◻︎パース(透視図法)の勉強にオススメの本
パース 透視図法の勉強におすすめの本4冊 イラストを上手く描こう!
◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

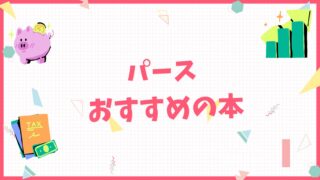

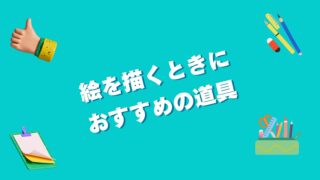
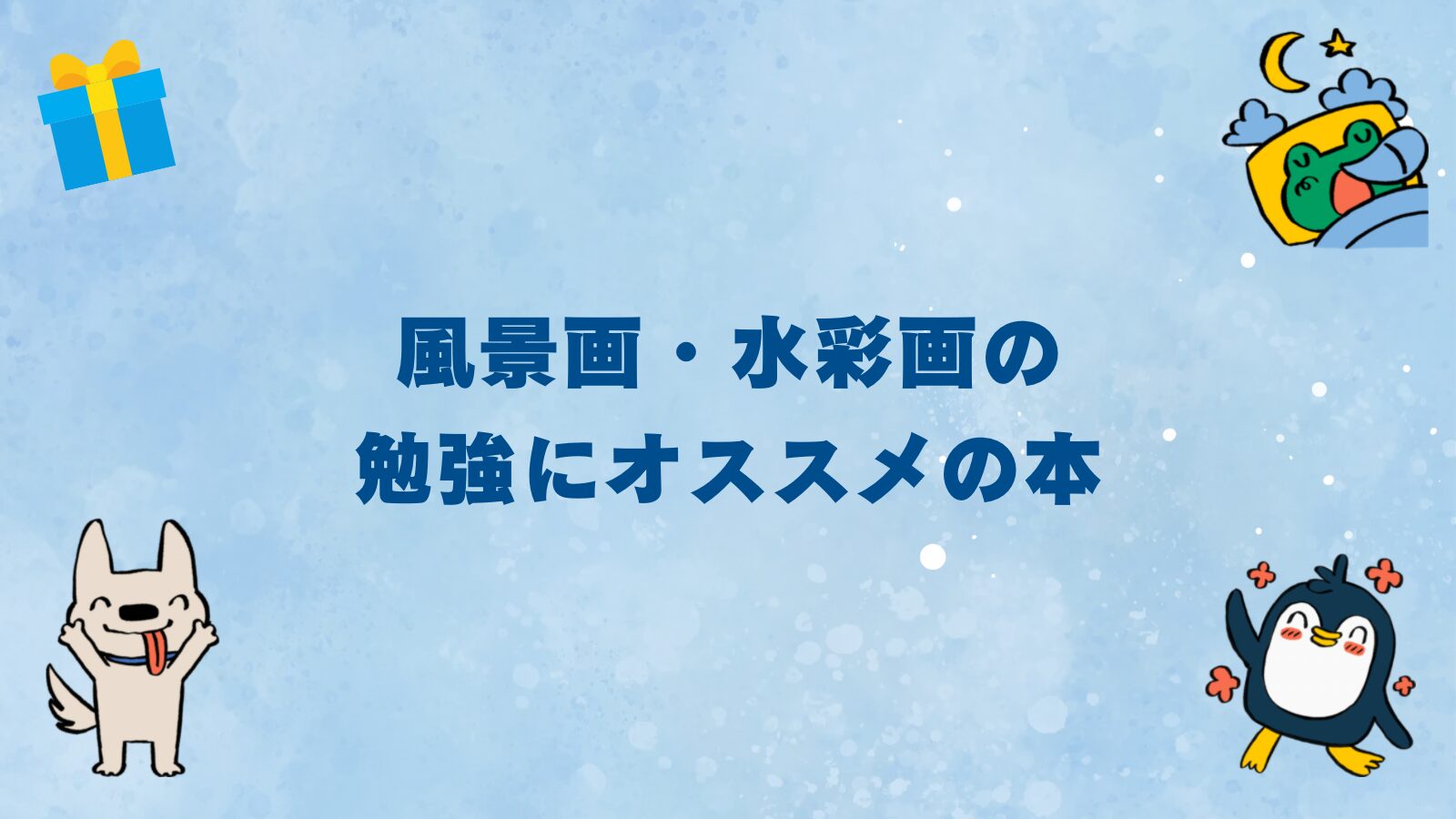

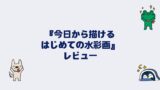

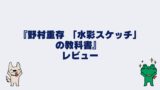

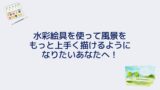

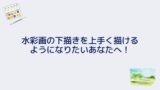



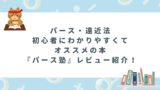

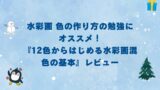


コメント